
SNSなどでふと見かける、息をのむほど美しい模様のショール。
その名は「枯山水ショール」。
ドイツご出身のニットデザイナー、ベルンド・ケストラーさんが生み出されたこの作品は、その独特の魅力で多くの編み物ファンを惹きつけているようです。
しかし、いざ編んでみたいと思うと、編み図はどこにあるのか、特徴的な編み方である引き返し編みは自分にもできるのか、どんな糸で編むのが最適なのか、そして完成まで難しいのではないか、といった様々な疑問が心に浮かぶかもしれません。
この記事では、枯山水ショールに関する様々な情報を集め、ご紹介します。作品の基本的な事柄から、具体的な編み方、多くの方が選ばれている毛糸のレビュー、そして制作の過程で直面しがちな課題を乗り越えるヒントまで、あなたの「知りたい」というお気持ちに寄り添えれば幸いです。
ポイント
-
枯山水ショールの基本的な特徴と魅力
-
編むために参考となる書籍や毛糸の情報
-
具体的な編み方のコツや注意点
-
完成後の活用方法やアレンジのヒント
枯山水ショールの基本情報

-
そもそも枯山水ショールとは?
-
考案者はベルンド・ケストラー氏
-
編む人を惹きつける枯山水ショールの魅力
-
編み図が掲載されている書籍
-
編み方はドイツ式引き返し編み
そもそも枯山水ショールとは?

まず最初に、枯山水ショールがどのような作品で、どのような背景から生まれたのか、その魅力や編むために不可欠な書籍について、少し詳しく見ていきたいと思います。
枯山水ショールは、その名の通り、日本の伝統的な庭園様式「枯山水」の砂紋を思わせる、流れるような美しい模様が印象的なニットショールです。
ドイツご出身のニット作家、ベルンド・ケストラーさんによって考案されました。
このショールの最もユニークな点は、その構造にあるようです。一般的な長方形や正三角形のショールとは異なり、小さな三角形を次々と編み足していくことで、全体として大きな非対称の三角形を形作ります。
この独特な構造が、段染め糸の色の変化と美しく調和し、まるで刷毛で描いたかのような趣のある模様を生み出します。
ほとんどの部分がガーター編みで構成されているため、編み方のルールさえ覚えてしまえば、比較的取り組みやすいのも人気の理由の一つのようです。
しかし、そのシンプルな工程から生まれる作品は非常に表情豊かで、纏うだけで装いの主役になるほどの存在感を放つように感じられます。
考案者はベルンド・ケストラー氏

枯山水ショールの生みの親であるベルンド・ケストラーさんは、ドイツのヘッセン州ダルムシュタットご出身のニットデザイナーです。
10代から独学で編み物を始められ、1998年に来日されて以来、日本を拠点に活動されています。
ケストラーさんの作品は、ヨーロッパの伝統的な技法を基にしながらも、日本の編み物ファンが親しみやすいように工夫されているのが特徴です。
特に、日本の編み物の本が持つ「記号化された編み図」という文化を高く評価されているそうで、言葉の違いを越えて誰もが編み物を楽しめる可能性を追求されています。
ケストラー氏の多彩な活動
ケストラーさんは、枯山水ショール以外にも「スパイラルソックス」や「ブリオッシュ編み」など、数々の人気作品を生み出されています。
その根底には、「編み物はもっとシンプルで、楽しく、自由なものであってほしい」というお考えがあるようです。
難しいと思われがちな技法も、ケストラーさんの手にかかると分かりやすい「ケストラー式」として紹介されています。
また、東日本大震災の被災地にニットブランケットを届ける「Knit for Japan」というプロジェクトを立ち上げるなど、編み物を通じた社会貢献活動にも熱心に取り組んでいらっしゃいます。
バイクを愛し、ツーリングの合間に編み物をされるというスタイルからも、その自由で温かいお人柄がうかがえます。
編む人を惹きつける枯山水ショールの魅力

枯山水ショールがこれほど多くの編み物愛好家から支持される理由は、主に二つの魅力があるようです。それは「無心になれる作業の楽しさ」と「段染め糸の美しさを存分に活かすデザイン」ではないでしょうか。
一つ目の魅力は、その編み方にあります。基本的なルールを一度理解してしまえば、複雑な編み図を常に確認する必要がなく、ひたすら手を動かすことに没頭できると言われています。
この繰り返しの作業が、日々の悩みやストレスを忘れさせてくれる、一種の「作業療法」のようだと評する方もいらっしゃいます。ただ静かに編み進めるうちに、編み地が少しずつ育っていく達成感や充足感は、何物にも代えがたいもののようです。
そしてもう一つの魅力は、デザインそのものです。段染め糸を使って編むことで、色の変化が三角形の連なりと見事に調和し、予測できない美しい模様を描き出します。
同じ糸を使っても、色の出方によって全く違う表情の作品が生まれるため、完成するまでどのような模様になるかわからない期待感も楽しめます。まさに、糸が持つ可能性を最大限に引き出してくれるデザインと言えるかもしれません。
編み図が掲載されている書籍
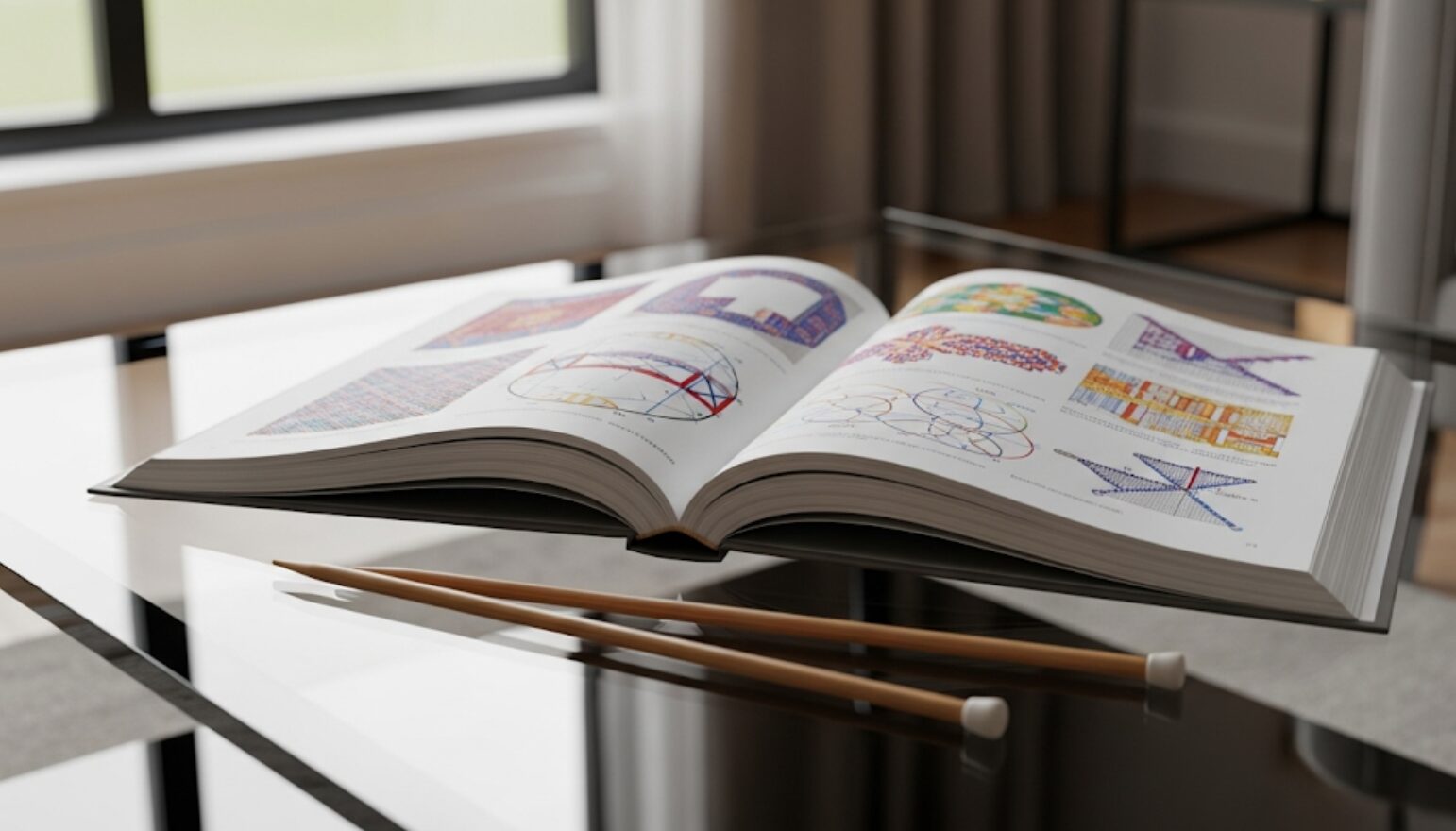
枯山水ショールの編み図は、ベルンド・ケストラーさんの著書『ベルンド・ケストラーの引き返し編み ドイツ式だからすいすい編める』(世界文化社)に掲載されています。
この書籍は、枯山水ショールのためだけのものではなく、「ドイツ式引き返し編み」という技法を主題にした作品集です。日本では「引き返し編み」というと、靴下のかかとなど特定の箇所で使われる、少し複雑な技法という印象があるかもしれません。
しかし、この本で紹介されているドイツ式は比較的シンプルで、一度覚えると様々な形やデザインに応用が利くとされています。
書籍には、枯山水ショール以外にも、同じ技法を用いたショールや帽子、ウェアなど、多彩な作品が掲載されています。
そのため、枯山水ショールを編む目的でこの本を手に取った方が、他の作品の魅力にも触れ、さらに編み物の世界の奥深さに心を惹かれるケースも多いようです。
編み方はドイツ式引き返し編み

枯山水ショールの特徴的な形を生み出している背景には、「ドイツ式引き返し編み」という技法があります。これは、編み地の途中で編む方向を変えたい際に使われるテクニックで、英語では「ジャーマン・ショート・ロウ」とも呼ばれています。
この技法を用いることで、編み地に不自然な穴を開けることなく、滑らかなカーブや傾斜を作り出すことが可能になります。枯山水ショールでは、この技法を繰り返し用いることで、あの美しい三角形の連なりを形成していくのです。
ケストラーさんが紹介するドイツ式引き返し編みは、従来の日本の方法(ラップ&ターンなど)と比べて、手順がシンプルで覚えやすいと言われています。
とはいえ、編み物が初めての方や、引き返し編みにあまり馴染みのない方にとっては、最初の数ブロックを編む際に少し戸惑うこともあるかもしれません。
しかし、多くの経験者が語るように、この最初の段階を乗り越え、編み方の「ルール」を体で覚えると、あとは驚くほどスムーズに編み進められるようになるとのことです。
まるで「開眼する」ような瞬間が訪れると言われており、そこからは無心で編む楽しさを満喫できるのではないでしょうか。
枯山水ショールを編むための実践ガイド

みんなはどんな糸で編む?毛糸レビュー 完成までの道のりは難しい? 引き返し編みのトラブルはある? サイズを自分好みに調整するヒント 完成したショールの活用アイデアを紹介
みんなはどんな糸で編む?毛糸レビュー

ここからは、実際に枯山水ショールを編む上で役立つかもしれない、より具体的な情報をお届けします。
糸選びのヒントから、制作過程での留意点、サイズ調整のコツまで、あなたの挑戦を少しでも後押しできれば嬉しいです。
枯山水ショールを編む上で最も楽しい時間の一つが「糸選び」かもしれません。このショールは、段染め糸(グラデーションヤーン)で編むことが勧められています。
なぜなら、色の変化がショールの構造と響き合い、思いがけない美しい模様を生み出してくれるからです。また、単色の糸で編むよりも、引き返し編みの際に少し出てしまうかもしれない編み目の不揃いが目立ちにくいという利点もあるようです。
ここでは、多くの方が実際に使用されている人気の毛糸をいくつかご紹介します。
|
毛糸ブランド/商品名 |
メーカー/販売元 |
特徴 |
編んだ人の感想やポイント |
|---|---|---|---|
|
yu-yake(ユウヤケ) |
ごしょう産業 (毛糸ピエロ) |
ウール100%の中細糸。日本の夕景をイメージした美しいグラデーションが人気です。色の変化がゆっくりなのも魅力。「ソラ」「よいのくち」など詩的な名前が付けられています。 |
滑りが良く編みやすいとの声があります。色の出方がとても美しいようです。リニューアルされて玉巻きで販売されているものもあります。 |
|
Opal(オパール) |
TUTTO (ドイツ) |
ソックヤーン(靴下用毛糸)の代表的なブランド。非常に多くの色柄があります。特にフンデルトヴァッサーシリーズは芸術的な色使いで人気が高いようです。 |
耐久性があり、チクチク感が少ないと言われています。単色と組み合わせて編むアレンジも素敵です。4〜5玉で大判に仕上げた例も見られます。 |
|
Schoppel(ショッペル) |
Schoppel (ドイツ) |
ザウバーボールやザウバーフラワーなど、ユニークな色の変化で知られています。ケストラーさんの書籍でも使用されていることが多いようです。 |
柔らかい風合いで、編みやすいとの感想があります。特に明るい色合いのものは、編んでいる時間も楽しい気持ちにさせてくれるようです。 |
|
Alize Bella Batik(アリゼ ベラ バティック) |
Alize (トルコ) |
コットン100%の夏向きの糸です。さらりとした肌触りで春夏のショールに適しています。鮮やかな色の組み合わせが特徴的です。 |
糸割れしにくく編みやすいと言われています。糸玉で見るよりも、編むと濃い色が多く出る傾向があるかもしれません。綿素材なので少し重さが出る可能性もあります。 |
|
おとなグラデーション |
セリア (100円ショップ) |
アクリル100%で手に入りやすいのが魅力です。落ち着いた色味のグラデーションが揃っています。気軽に挑戦してみたい場合に良いかもしれません。 |
軽く仕上がるとの声があります。ただ、途中で糸が足りなくなる可能性を考え、少し多めに購入しておくと安心かもしれません。 |
これらの他にも、様々な段染め糸で素敵な作品が作られています。ご自身の好きな色合いや素材、予算に合わせて、お気に入りの糸を見つける時間も、枯山水ショール作りの楽しみの一つです。
完成までの道のりは難しい?

「枯山水ショールは編むのが難しいのか」という問いには、「技術的な難易度はそれほど高くないかもしれませんが、完成には時間と根気が必要になるかもしれません」とお答えするのがしっくりくるかもしれません。
このショールは、小さな三角形から始まり、徐々に大きな三角形を編み足していく構造です。そのため、編み始めは比較的すんなりと進み、編み地が育っていく様子を目で見て楽しむことができます。
しかし、プロジェクトが進むにつれて、一つの三角形を編むのに必要な目数と段数がだんだんと増えていきます。
後半に感じられるかもしれない挑戦

多くの経験者が語るように、ショールが大きくなるにつれて、1段を編むのにかかる時間が長くなっていくようです。また、編み地全体の重みが増してくるため、手にかかる負担も少し大きくなるかもしれません。
この段階で、モチベーションを保つのが一つの挑戦となる可能性があります。
さらに、目を落としてしまったり、編む方向を間違えたりといった失敗も起こることがあります。特に、しばらく間が空いてから編み物を再開した際に、どこから編み進めるべきか分からなくなり、三角形の形が崩れてしまうケースは少なくないようです。
そうなると、ある程度の量をほどいてやり直す必要が出てくることもあります。
しかし、こうした道のりの先に、大きな達成感が待っています。少しずつ現れる美しい模様が、きっとあなたの支えになります。
焦らず、ご自身のペースでゆっくりと育てていくような感覚で取り組むのが、完成への一番の近道と言えるかもしれません。
引き返し編みのトラブルはある?

枯山水ショールを編む上で、多くの初心者の方が気にされる点の一つが「引き返し編みの部分がデコボコしてしまう」ということのようです。
これは、ドイツ式引き返し編みの構造上、ある程度は仕方のない現象のようです。
引き返し編みでは、編み地の途中で方向を変えるために「ダブルステッチ」という操作を行います。
後でこのダブルステッチを隣の目と一緒に編むことで段差を解消するのですが、どうしてもその部分だけ糸が重なるため、他の部分と比べて編み地にわずかなデコボコができてしまうことがあります。
デコボコを目立たなくするためのヒント
このデコボコ感を完全になくすことは難しいかもしれませんが、目立たなくするためのヒントがいくつかあります。
まず一つ目は、ケストラーさんご自身が推奨されているように「段染め糸を使う」ことです。色の変化に自然と視線が向かうため、編み地のデコボコが相対的に目立ちにくくなると言われています。
単色の糸、特に撚りがしっかりした糸で編むと、このデコボコ感がより分かりやすくなる傾向があるようです。
二つ目は、仕上げの工程を丁寧に行うことです。完成したショールを水通し(またはスチームアイロンを浮かせてかける)することで、編み目が落ち着き、デコボコがかなり和らぐ場合があります。
特にウールなどの天然繊維は、この仕上げの工程で風合いがぐっと良くなることが知られています。
完璧な仕上がりを目指すあまり、このデコボコ感が気になってしまうかもしれません。しかし、これは技法の特性であり、多くの作品に見られるものです。
手編みならではの風合いとして受け入れ、楽しむくらいの気持ちでいるのが良いかもしれません。
サイズを自分好みに調整するヒント

枯山水ショールの優れた点の一つに、サイズの調整がしやすいことが挙げられます。書籍に掲載されているパターンでは、基本的に12個の三角形を編んで完成とされていますが、これはあくまで一つの目安です。
使用する糸の太さや、編む方の手の加減(ゲージ)によって、同じ段数を編んでも完成サイズは変わってきます。また、ショールをどのように使いたいかによっても、最適な大きさは人それぞれです。
三角の数でサイズを調節
このショールは、いつでも好きな大きさで終えることができます。例えば、少し小ぶりなネックウォーマーのように使いたい場合は、三角形の数を8個や10個で終えても、素敵な作品になります。
逆に、体をすっぽりと覆うような大判のショールにしたい場合は、12個以上編み進めることもできます。
サイズ調整の分かりやすい方法の一つは、毛糸の量に合わせて決めることです。例えば、100gの毛糸を2玉用意した場合、「2玉を使い切るところまで編む」という目標を立てることができます。
実際に、2玉(約700m〜800m)で、日常使いにちょうど良いサイズのショールを完成させている方も多くいらっしゃいます。
編み進めながら、時々ご自身の肩に羽織ってみて、好みの大きさになったかどうかを確認するのもおすすめです。このように、編む人の思い通りにサイズを決められる点は、このパターンの持つ大きな魅力です。
完成したショールの活用アイデアを紹介

時間をかけて丁寧に完成させた枯山水ショールは、様々な場面で活躍するアイテムになるのではないでしょうか。その独特の形と美しい模様は、実用性とファッション性を兼ね備えています。
最も一般的な使い方のひとつは、肩からふわりと羽織るスタイルです。非対称の三角形なので、片方の肩に長く垂らしたり、首元にくるくると巻いたりと、アレンジ次第で多彩な表情を見せてくれるようです。
春先や秋口の少し肌寒い日には、上着代わりとしても重宝するのではないでしょうか。
また、多くの方が実践されているように、オフィスでの冷房対策としても役立ちます。アクリルなどの軽い糸で編んだものであれば、小さくたたんでバッグに入れておいてもかさばりにくいです。膝掛けとしても使用でき、一枚あると何かと便利かもしれません。
さらに、その美しいデザインから、大切な方へのプレゼントとしても喜ばれるようです。編む人の温もりが伝わる手編みのショールは、特別な贈り物になるのではないでしょうか。
贈る相手の好きな色合いの糸を選んで編む時間もまた、素敵なひとときです。
この記事では、ベルンド・ケストラーさんが考案された枯山水ショールについて、その魅力から具体的な編み方、多くの方が抱く疑問まで、様々な情報をご紹介しました。最後に、このショールを編むことの楽しさや価値について、大切なポイントをまとめてみたいと思います。
枯山水ショールを編む楽しみ
-
枯山水ショールは日本の庭園様式に着想を得た美しいニット作品
-
考案者はドイツご出身のニットデザイナー、ベルンド・ケストラーさん
-
特徴的な模様はドイツ式引き返し編みという技法から生まれる
-
編み図は書籍『ベルンド・ケストラーの引き返し編み』に掲載されている
-
段染め糸を使うことでデザインの魅力が一層引き立つ
-
人気の毛糸にはOpalやユウヤケ、ショッペルなどがある
-
基本的な編み方はシンプルで無心になって編む楽しさがある
-
完成までの道のりは長く、特に後半は根気が必要になることもある
-
技術的な難易度は高くないため、編み物初心者の方も挑戦しやすい
-
引き返し編みによる編み地の凹凸は技法上ある程度生じるもの
-
段染め糸の使用や仕上げのスチームで凹凸は目立ちにくくなる
-
完成サイズは三角形の数を増減させることで自由に調節できる
-
書籍のパターン通り12個の三角にこだわる必要はない
-
肩から羽織ったり首に巻いたりと様々な使い方が楽しめる
-
オフィスの冷房対策や膝掛けとしても実用的
-
手作りの温かみがあるため、プレゼントとしても喜ばれる
この投稿をInstagramで見る