
食育アドバイザーの資格は意味ないと考える方は少なくありません。
特に、「民間資格だから役に立たないのでは?」「就職や転職に直結しないのでは?」という不安を持っている方も多いでしょう。
確かに、国家資格のように法的な効力があるわけではないため、食育アドバイザーを取ったからといってすぐに仕事が決まるとは限りません。
しかし実際には、家庭や職場、地域社会の中で"食"に関する正しい知識を持っていることが求められる場面は多く、資格取得によって生活や仕事に活かしている方もいます。
この記事では、芸能人の取得例や、仕事や日常生活での活用方法、そして食育アドバイザーと食生活アドバイザーの違いについてもご紹介します。
ポイント
-
食育アドバイザーとはどのような資格で何を学ぶのか
-
食育アドバイザーが仕事や日常生活でどう活かせるか
-
国家資格との違いや評価されるポイント
-
食育アドバイザーと食生活アドバイザーの具体的な違い
食育アドバイザーは意味ない?

-
食育アドバイザーとは何か?
-
食育アドバイザーと仕事の関係
-
芸能人も取得している資格
-
資格取得のための勉強法
-
食育アドバイザーの合格率はどれくらい?
食育アドバイザーとは何か?

食育アドバイザーとは、日々の食事や栄養について知識を身につけ、家庭や職場、地域でその知識を活かすための民間資格です。
料理や栄養のことはなんとなく自己流になりがちですが、正しい知識を学ぶことで「食」をもっと前向きに考えられるようになります。
「食育アドバイザーって何する人?本当に役に立つの?」と疑問に思う方は少なくありません。
特に、国家資格じゃないと聞くと「意味ないかも」と思ってしまうのも自然なことです。
でも実は、この資格は厚生労働省や文部科学省も重視している「食育」という分野に基づいていて、バランスの良い食事の組み立て方や食品の選び方、成長段階に応じた食生活の工夫など、暮らしに役立つ知識がたくさん学べます。
講座は比較的やさしく、最短1ヶ月ほどで取得できる手軽さもあり、子育て中の方や保育・介護などの仕事に携わる人たちにとても人気です。
医師や栄養士のような法的な業務権限があるわけではありませんが、「ちょっとした知識をきちんと伝えられる人」として周囲から信頼されやすくなる、そんな資格です。
このように、食育アドバイザーは“食”についてしっかり考えたい人や、周囲の健康をサポートしたいと願う人にとって、親しみやすくて実用的な資格なのです。
食育アドバイザーと仕事の関係

食育アドバイザーの資格は、単体で就職に直結するわけではありませんが、今の仕事にちょっとした強みを加えることができる資格です。
特に食に関わる場面がある職種では、知識を持っていることで好印象を与えられることもあります。
「この資格があれば、すぐに食の仕事ができるの?」と気になる方も多いと思います。
実際のところ、管理栄養士や調理師のような国家資格とは違って、特定の職業に就ける法的な効力があるわけではありません。
ただ、たとえば保育士さんや介護士さん、学校関係の職員、スポーツインストラクター、飲食業で働いている方など、日頃から“食”に接する仕事をしている人にとっては、この資格があることで「ちゃんと食について学んでいる人」という信頼感を持ってもらえます。
また、履歴書に記載すれば「食育を大切にしている人」「学ぶ姿勢のある人」といった前向きな印象を与えることができます。
最近では、健康や食に対する関心が高まっているので、そうした意識を持っていること自体が評価につながることもあるのです。
さらに、企業で健康を意識した取り組みをしているところや、地域の健康イベントなどでも、ちょっとしたアドバイスができるだけでも役立つ場面があります。
営業や事務の仕事をしている人でも、社内イベントでレクチャー役になるなど、意外なところでチャンスが広がるかもしれません。
このように、食育アドバイザーは「この資格だけで仕事が決まる」ものではありませんが、「今の仕事をもっと良くするための頼れる知識」として活かしていける資格です。
芸能人も取得している資格

食育アドバイザーの資格は、最近では一般の方だけでなく、芸能界でも注目されている資格のひとつです。
中でも、芸人として活躍する川島章良さんと、タレントの新山千春さんがこの資格を取得していることをご存じでしょうか。
「芸能人がどうして食育の資格を取るの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
華やかな世界にいる芸能人であっても、自分や家族の健康を気遣うことはとても大切なテーマです。
芸能人だから特別というよりは、「家族のためにできることを増やしたい」という想いが根底にあるように感じられます。
このように、有名人がこの資格を取得し、実生活で生かしている例を知ることで、食育アドバイザーは私たち一般人にとっても身近で実用的な知識だと感じられます。
芸能人がSNSなどで発信する日々の食事や工夫の様子は、多くの人にとってヒントになり、関心を持つきっかけにもなっています。
食育アドバイザーは「暮らしに密着した知識」として、多忙な芸能人の間でも活用されている資格です。
日常の中で自然と取り入れられるスキルだからこそ、注目されているのかもしれません。
資格取得のための勉強法

食育アドバイザーの資格は、忙しい人でも取り組みやすい民間資格として人気があります。
特に、子育てや仕事のスキマ時間を活かして学べる点が、多くの方にとって魅力となっています。
「そんなに手軽なら、通信講座を受けずに独学でも取れるのでは?」と思う方もいるかもしれません。
確かに、テキストを読むだけなら自分一人でもできそうに思えます。
しかし、実際に独学だけで合格を目指すのは意外とハードルが高いです。
また、この資格の受験には、あらかじめJADP(日本能力開発推進協会)指定の教育機関が提供する認定講座を修了する必要もあります。
つまり、講座を受けること自体が資格取得の前提条件になっています。
この講座では、食育の基礎から食品の安全性、食育活動の方法まで、幅広い内容が体系的に学べるようにカリキュラムが組まれています。
テキスト学習だけでなく、練習問題や添削課題、質問サポートなどもあり、分からない点を放置せずに進められるのが特徴です。
また、講座の内容は実生活に直結したものが多く、学んだ知識を家庭での食事や健康管理にそのまま活かすことができます。
たとえば、家族の栄養バランスを考えた献立づくりや、子どもに安心して食べさせられる食材の選び方など、日常に役立つヒントが満載です。
試験は在宅で受ける形式で、協会の公式サイトから申し込みを行い、課題をすべて提出して受験料(5,600円)を支払うと、自宅に問題が届きます。
合格には得点率70%以上が必要で、結果は1か月ほどで通知されます。
このように、食育アドバイザーの資格は「勉強しやすい」と言われていますが、独学だけでは取得が難しく、講座の受講が必須となっています。
しっかりと学びながら進めることで、日常生活にも役立ち、資格取得の自信にもつながるはずです。
また、食関連の資格取得のための基礎がわかり、取得後に別の食関連の資格への手がかりとしても活用できるでしょう。
食育アドバイザーの合格率はどれくらい?

食育アドバイザーの資格は、比較的チャレンジしやすい民間資格とされており、その合格率は高い傾向にあります。
「どれくらいの人が合格しているの?」と気になる方もいると思いますが、先述したとおり、食育アドバイザーの資格試験には、前提として資格講座の受講が必須とされています。
この資格は、日本能力開発推進協会(JADP)が認定するもので、受験するにはまず認定教育機関が提供する通信講座を修了する必要があります。
つまり、誰でもいきなり試験を受けられるわけではなく、きちんとしたカリキュラムをこなしたうえで初めて、在宅での試験にチャレンジできる仕組みになっています。
試験の合格基準は得点率70%以上とされています。
受講者は講座の中で試験範囲に含まれる「食育の基礎知識」「食品の安全性」「食育活動」などを学び、課題や模擬試験をこなして理解を深めていきます。
このような流れがあるため、学ぶべきポイントをしっかり押さえておけば、多くの方がスムーズに合格できる内容となっています。
実際、通信講座の添削課題やサポートも充実しており、初学者でも安心して学べる環境が整っています。
「簡単に取れる資格なんじゃないの?」と思う方もいるかもしれませんが、全くの知識ゼロから独学で合格するのはやや難しいとも言えます。
なぜなら、講座で提供される学習内容がそのまま試験に直結しているためです。
つまり、講座をしっかり受講した人にとっては合格しやすい資格であり、それが合格率の高さにつながっているのです。
無理なく勉強を続けられれば、十分に合格を目指せる資格と言えるでしょう。
食育アドバイザーは意味ないと思われがちな要素

-
国家資格との違い
-
食育アドバイザーと食生活アドバイザーの違い
-
食生活アドバイザー3級は難しい?
-
食生活アドバイザーは履歴書に書ける資格?
-
食育アドバイザーの資格が活かせる場面
国家資格との違い
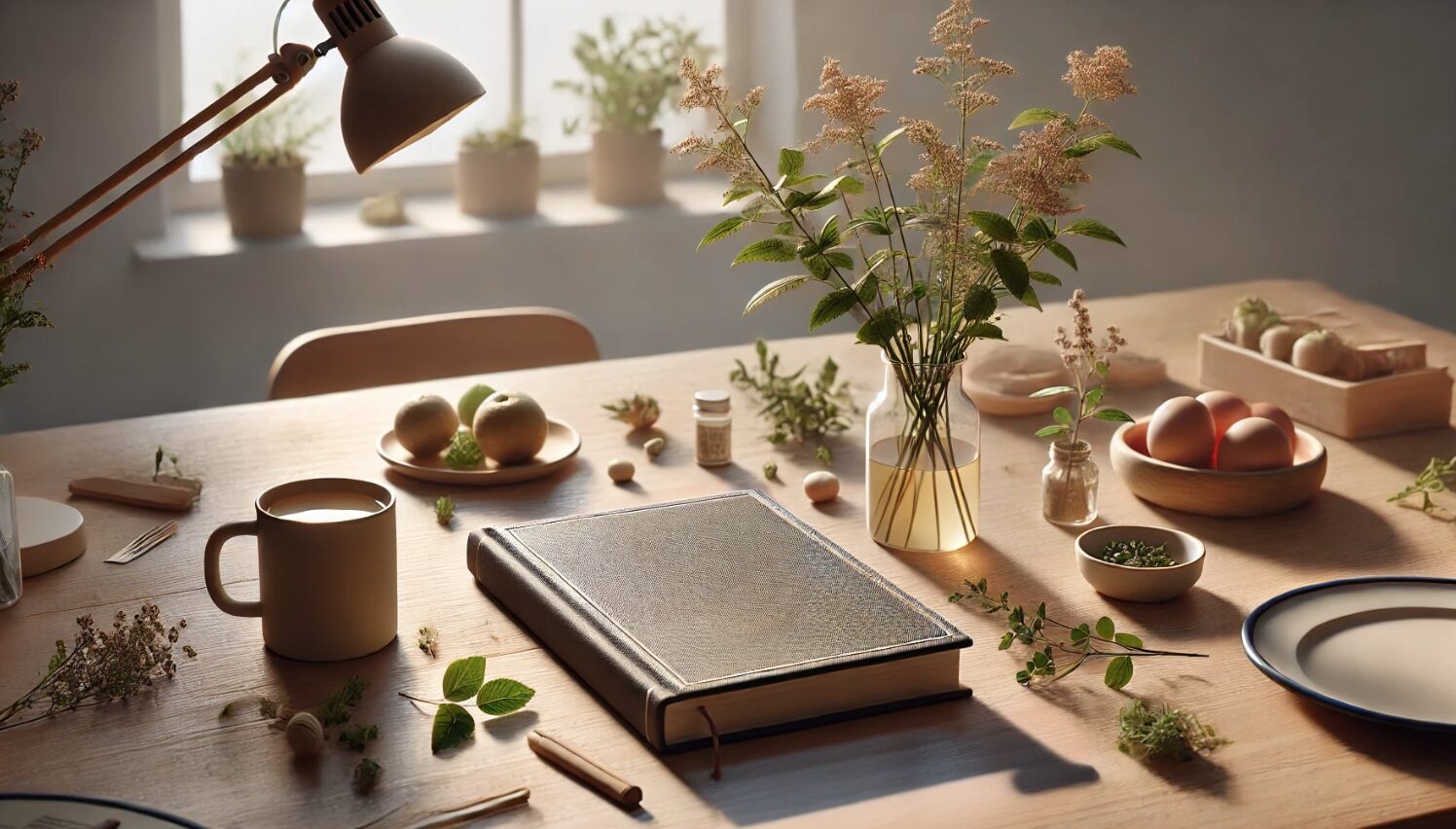
食育アドバイザーは、国家資格ではなく民間資格です。
この点が「意味ないのでは?」と感じるきっかけになることがあります。
国家資格というと、たとえば管理栄養士や栄養士が挙げられます。
これらは大学や専門学校などで専門的な教育を受け、国家試験に合格する必要があります。
そのため、医療現場や学校、行政機関などでの業務に直接関わることが可能です。
一方、食育アドバイザーは、特定の国家試験を受ける必要がなく、認定された教育機関の講座を修了し、在宅で試験を受けることで取得できます。
これが「手軽すぎる」「誰でも取れる」と見られてしまい、資格としての重みが軽く感じられることもあるのかもしれません。
ただ、このように考えると、食育アドバイザーは専門職としてのキャリアを築くための資格というよりも、日常生活や仕事に知識をプラスするための資格と言えます。
たとえば、保育士、介護士、料理教室の講師など、他の職種と組み合わせて活用することで、知識を深めることができます。
国家資格と比べると、確かに就職や転職の際に直接的な採用条件にはなりにくいかもしれません。
また、履歴書にこの資格を記載することで、「食や健康に関心がある人」というプラスの印象を与えることができる可能性があります。
とくに、保育や福祉、飲食関連の仕事を希望している場合には、採用担当者の目にも留まりやすくなるかもしれません。
そして何より、自分や家族の毎日の食事に役立てられる点が、この資格の一番の魅力です。
食育アドバイザーと食生活アドバイザーの違い

食育アドバイザーと似たような名前の資格に「食生活アドバイザー」があります。
この二つの資格について「どちらが良いの?」「具体的に何が違うの?」と疑問を持つ方は少なくありません。
まず、食育アドバイザーは、主に家庭内や地域社会など、身近な場所で食の重要性を伝えることを目的とした資格です。
学ぶ内容としては、子どもや高齢者といった健康に特に気を配る必要のある人たちに対して、どういった食事のサポートができるかを中心に、食の安全性や栄養バランス、そして「食育」という考え方そのものについても学びます。
講座では、実生活に結びついた知識を基礎から体系的に学ぶことができ、学んだことは家庭内の食事の工夫や、地域での食に関する活動にも活かせます。
それに対して、食生活アドバイザーは、より消費者寄りの視点で生活全体の中にある食の位置づけを学んでいく資格です。
こちらは栄養学や食品に関する知識はもちろん、マナー、買い物に関する知識、さらには流通についてまで幅広く取り扱います。
実際の試験は日本能力開発推進協会(FLA)によって実施され、3級と2級の2つのレベルがあります。
学習範囲が広いため、自分の生活スタイル全体を見直したい人や、食関連の知識を総合的に深めたい人に人気があります。
つまり、両者の大きな違いは目的の違いにあります。
食育アドバイザーは「誰かに食の大切さを伝えたい人」、たとえば子育て中の方や教育関係の方に適しており、食生活アドバイザーは「自分自身の食生活をもっと豊かにしたい人」に向いています。
ただし、学ぶ内容には共通点も多く、どちらも日常生活に役立つ知識が詰まっている点では同じです。
「家族や子どものために、より健康的な食生活を意識したい」という目的であれば食育アドバイザーが、「買い物や調理、マナーまで幅広く食の知識を活かしたい」という方には食生活アドバイザーがぴったりでしょう。
食生活アドバイザー3級は難しい?

食生活アドバイザー3級の試験は、思ったよりも難易度が高いと感じる方が多いようです。
「3級だから簡単そう」と考える方もいますが、実際に勉強を始めると、その内容の幅広さに驚かされることがあります。
たとえば、栄養素や食品の分類だけでなく、衛生管理、食文化、マナー、さらには流通や消費者問題まで出題されるため、暗記だけでは厳しいものがあります。
では、なぜ3級でも難しいと感じるのでしょうか。
それは、生活に密着した内容を幅広く学ぶ必要があるからです。
試験範囲はとても実用的で、普段の生活に関係していることが多いため、一見すると覚えやすいように感じるかもしれません。
しかし、いざ試験勉強となると、内容の多さに加え、それぞれの分野で細かい知識が問われるので、思っていた以上に準備が必要になります。
さらに、受験者の中には、学生よりも社会人の方が多く、自分の時間を確保しながらコツコツ勉強する必要があります。
このような事情もあり、勉強のペースを保つことが難しく、試験に対してハードルが高いと感じる人が出てくるようです。
ただし、学ぶ内容はどれも日常生活に役立つ知識ばかりなので、勉強を続けることで、自分の食生活が少しずつ改善されていく実感を得られるでしょう。
その意味では、たとえ合格を目指すにしても、結果以上に得られるものが多い資格ともいえます。
食生活アドバイザーは履歴書に書ける資格?

食生活アドバイザー2級は民間資格なので、「民間資格って、履歴書に書いていいの?」と迷う方は多くいます。
特に、国家資格ではないため、意味があるのかどうか不安になるのも無理はありません。
しかし、食生活アドバイザーは広く知られている資格の一つで、日本能力開発推進協会(FLA)が主催し、一定の審査基準をもとに行われている資格試験です。
そのため、食品関連の仕事など、業務的に関係のあるのであれば履歴書に記載してアピールができます。
実際に、食や健康に関する職業、たとえば保育園、福祉施設、食品メーカー、小売業などでは、この資格を持っていることで、一定の知識を持っている証明として評価されることもあります。
もちろん、履歴書に書くだけで即戦力と見なされるわけではありませんが、自己PR欄や志望動機とあわせて「なぜこの資格を取得したのか」「どのように活かしたいか」をしっかり書くことで、採用担当者に良い印象を与える可能性は十分にあります。
また、就職や転職に限らず、自分や家族の健康を守る知識としても有用なので、取得しておいて損はない資格といえるでしょう。
食育アドバイザーの資格が活かせる場面

食育アドバイザーの資格は、取得してもすぐに職業が決まるようなものではありませんが、さまざまな場面で知識を活かすことができます。
では、どのようなシーンでこの資格が役に立つのでしょうか。
まず、子育て中の方にとっては、毎日の食事作りの中で栄養バランスを意識したり、子どもの食への関心を高める工夫を理解しておくことが、とても役に立ちます。
例えば、偏食がちな子どもにどうアプローチするか、野菜を美味しく食べてもらうための工夫など、学んだことを日常にそのまま取り入れることができます。
こうした家庭での実践は、家族全体の健康にもつながります。
また、保育士や介護士、学校関係者など、子どもや高齢者に関わる仕事をしている人にとっても、この資格は知識の補強になります。
食事指導や食事介助の場面で、根拠ある説明ができるようになると、信頼感が高まりますし、より丁寧な対応が可能になります。
さらに、飲食業界や食品販売に関わる人にとっても、食育の知識があることで、お客様との会話の中にプラスの価値を提供できるようになります。
単に食材の説明をするだけでなく、その背景や健康への影響まで話せることで、他のスタッフとの差別化につながるかもしれません。
自宅で料理教室を開きたいと考えている方にも、この資格はおすすめです。
資格取得を通じて得た知識や理論を土台にすることで、生徒さんに安心感を与えられますし、教室の信頼性も高まります。
このように考えると、食育アドバイザーの資格は、必ずしも一つの職業に直結するものではありませんが、「今の自分の活動に食の知識をプラスしたい」という人にとって、とても役立つ存在だと言えます。
特に、生活や仕事の中で人と食をつなぐ役割を担っている人にはぴったりの資格です。
食育アドバイザーが意味ないとは限らない理由
-
食育アドバイザーは日常生活に役立つ知識が身につく
-
家庭での健康的な食事作りに活かせる
-
保育や介護など現場での信頼につながる
-
食関連の接客業で差別化が可能
-
SNSや地域イベントでの発信に活用できる
-
認定講座を修了することで受験資格が得られる
-
試験は在宅で受けられ、取り組みやすい
-
合格率は高めで学習の継続がしやすい
-
川島明さんや新山千春さんも資格を取得
-
家族の健康を考える芸能人に支持されている
-
独学では受験できず、講座受講が前提
-
食生活アドバイザーとは学ぶ目的や範囲が異なる
-
資格取得後、他の食関連資格のステップにしやすい
-
資格があることで履歴書に前向きな印象を与える
-
一つの職業に直結せずとも現職に知識をプラスできる
この投稿をInstagramで見る